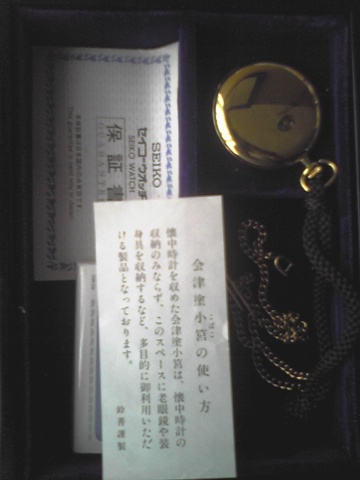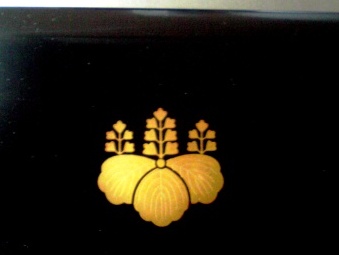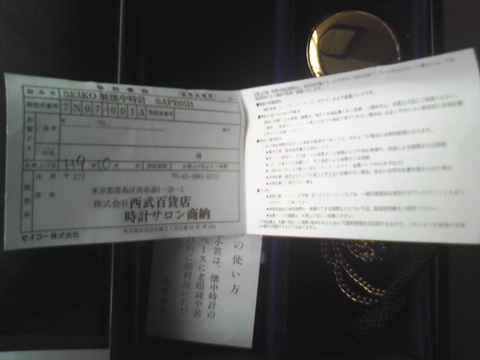藤本ナイフのアーミータイプモデル2本。
どちらも、約40年~60年前に製作された貴重なモデルの未使用品。メインブレードの他、缶きり、栓抜き(先端はドライバー)が付いている。時代の流れか、現代では栓抜きは不要かも。
また、炭素鋼を使用したモデルは大変珍しいらしく、未使用で発見するのは困難との意見もある。
アーミータイプのツールナイフでは、スイスのビクトリノクスやウェンガーのソルジャーが大変に有名。
同種のタイプで、まともに利用できる国産の市販ナイフは、過去・現在ともに日本では藤本ナイフ以外に存在しないと思う。市販といっても、当時の製品は、ほぼ手作り為の準カスタムに近い。
刃厚があり丈夫な造りの上に、必要最低限の機能を装備してしいるので、通常のキャンプ等にも十分に使用可能。メジャーなビクトリノクスも良いけれど、古い日本の製品には味があるように思える。 上の一本目は、めずらしいブレード形状のモデル#35。
上の一本目は、めずらしいブレード形状のモデル#35。
マークから判断して、こちらの方が製造年は古いと思われる。
刻印はないが、多分、炭素鋼。繊細なイメージの造り。
ブレードは72mm、ウッド部(丸型)、ハンドル長96mm。
下のモデルは、炭素鋼(正鋼)73mm、ウッド部(平型)、ハンドル長95mm。こちらの方が造りがガッシリとしている。
「正鋼」の刻印がリカッソの裏面に打刻されている。
今回紹介した2モデルの現状価格について一言。
前も書き込んだが、東京のショップで似たような中古のモデルに、一本100,000円を越す価格が付いていたり、ましてや時価だったりする事は、いくら価値基準のひとつとして考えても、少々複雑な心境である。それを見ると、もったいなくて安易に使用する気にはなれない。
※11/28 ある有名な藤本ナイフの紹介サイトで#35の情報がありましたので参考まで。
セン抜きと缶切りとその背バネと真中のスペーサーはステンレス。
2本あるライナーは両方とも真鍮。メインブレードとその背バネはスチール。・・・だそうです。
やはり、手の込んだ材料選択と細工のようです。
参考サイト:http://www4.ocn.ne.jp/~nunokiri/fujimoto4.htm
藤本ナイフの資料やご意見の書き込みは、大変、参考になり勉強させていただきました。
有り難うございました。